|
☆☆☆7、First love……☆☆☆ 五時間目、色々あった昼休みを終えて教室に集まった面々は、皆何処か重々しい顔つきだった。そしてその中に、蘭は居ない。 クラス中の視線を集めて教室に戻って来た新一もまた、暗い顔で無言のまま希美の隣に座った。 先程、園子と言い合って、ご機嫌よろしくなく教室に帰って来た希美だが、蘭と出て行ったと聞いていた新一が一人で戻って来たという事は何かある。そう勘ぐるのは容易な事だった。 「……どうかした? 新一」 「何が?」 彼は、穏やかに微笑して答えた。その笑みの意味は、周りに辛さを伝染させるのが嫌な故のものか、はたまた心配される事が嫌いなのか。 殆どいつもと変わらぬ素振りに、新一の心境の揺れを感じたのも、希美のもつ男用テクニックの一つである、相手の気分を読み取る事が出来なければ不可能だった。 あまりつつかれるのは好かないだろうと判断して、希美の次の口調は、彼の調子に合わせる何気なさを装った。 「ちょっと、いつもと違うな〜って思ったから」 「そうか? んな事ねえよ」 応えた新一は、普通に数学の教科書とノートを取り出して、どこかやる気なさげに頬杖をついた。 彼の態度は、全くいつも通りの仕草だ。蘭は、授業が始まった今になっても、教室に戻る気配を見せない。 (……つまり、何かあったのね) ほころびが出来た、と直感した希美は、隣に気づかれないように小さくシニカルな笑いを零す。 黒板に白いチョークで書かれる数式を、ただクールにノートに写しながら、希美は思考にふけった。 (ついに第一のほころび作りに成功よ。ちくちく、彼女に心理攻撃仕掛けた甲斐があったわね。親友の女の存在にはむかついたけど、いいわ。これでもうすぐ彼は私のものなんだから。) 内側からこみ上げて来る笑いを抑えながら、ノートを方程式で埋めていく希美は、けれども微かに、間逆の思いも感じていた。 段々と、ノートの上を走るシャープペンシルが勢いを落とす。いつもとは違う、感じたことのない”何か”。それが、少しずつ希美の心を支配してゆくのだ。 数学の時間中、結局帰らなかった蘭の机と、教室の戸を心配そうに伺う彼に気づいてしまったからだ。けれども、つきん、と痛みが走った理由が、彼女にはどうしても理解できない。 (何よ、この感じ……彼女と何かあったんでしょ? 嬉しい事じゃない。現にこんなに笑いがこみ上げてきそうな。なのに、どうして…………) 五時間目終了の報せがなるなり、クラスメイト達がどっと新一の周りを囲んだ。蘭と何があったのか、蘭に何を言ったのか、と口々に新一に質問をして、あわや告白でもしたのではないかと勘ぐる者も居た。 そう。皆、蘭がいない事を少なくも怪訝に感じていた。それに対して、どこか苦しげな引きつった笑みを浮かべ答える新一を見るのが、希美にはまた、痛かった。 (……クラスメイトにまで支持されているのね、あの二人。まぁ、私が新一からおこぼれするのを狙ってる奴もたくさんいるでしょうけど。でも、誰にも文句は言わせないわよ。……私が、新一を仕留めて見せるんだから。いい男を手に入れようとする事のどこが、いけないって言うのよ。) 彼女は、そこに居る全ての皆と、六時間目直前にぼんやりと帰って来た蘭、そして怒った顔で自分を睨みつけてくる園子に、心の中で文句を言った。 あともう一つは、自分自身に言い聞かせる意味もこめて。自分が今している事は、決していけない事なんかではないのだ、と。 心ここにあらずの状態で教室に戻り、席に着いた蘭を、新一はじっと見つめていた。何か言いたそうな視線で。 彼の気持ちも蘭にある事は、希美にも判っていた。けれども、いずれその視線を向けるのは、蘭ではなく自分になる、と。この時、まだ彼女は強く信じて疑わなかった。 (だって、折角見つけた私につりあう男よ。あの笑顔も、苦しい顔も、探偵としての凛々しい顔も。どれも私が隣に居ればもっと栄えるわ! 彼は……誰にも、渡さない。絶対、私のもの…………) 六時間目が終わり、帰りのHRでも、彼と彼女の態度は変わる様子がなかった。 一日の終了を告げるチャイムがなり、皆一斉に席を立つ。更なる作戦を開始する、と考えた希美は、すかさず隣の彼に明るい口調で言った。 「新一、今日私の家来ない? もう今日は部活もオフだし」 帰り支度をしながら教科書類を鞄につめる彼と、そして斜め前でまた同じように帰り支度をする蘭が、その言葉に反応した。 希美は、思い出したように蘭の方にもくるりと向き直る。 「蘭ちゃんも、一緒にどう? ……三人で、そうね、ゲームでも」 「え? わ、私は……」 蘭は、困惑した表情で新一の顔色を窺った。 昼休みあんな話をしたばかりだ。何となく、新一の隣に行くのが怖かったのだ。 勿論、元々そんな関係になかったのだから、別に何も恐れる事はないと言えども、気まずさはある。 どうしていいのか判らず、蘭は無言で新一を見つめた。そんな戸惑いを込めた視線に居心地の悪さを感じて、それを向けられた彼は、ふいと目をそらした。 「どうしたの? ほら。遠慮しないで。ウチの事なら大丈夫よ、越してきてから一週間は経つんだし、もうとっくに家の中綺麗に片付いてるから」 二人を見て、白々しく首を傾げながらも、再び明るい口調で言った希美。新一はそれを聞きながら隣で帰り支度を済ませ、不意にちらりと横目で蘭を見た。 何時もと違って何処か冷たさを覚えるその瞳に、蘭はびくりと表情を歪めた。その表情に気付いた彼は、少し考えてから答える。 「……いいんじゃねーか? 女は女同士。俺は今日ちょっと無理だから行けねーけどよ」 「そっか、新一は来れないのね、残念」 はぁ、と物足りなさげに溜め息をついた希美に、彼は、悪いな、とだけ付け加えた。 その後、再び数秒……彼は無言で蘭を見つめた後、再びふいと目を外し、鞄を肩に担ぎながらどちらにともなく言った。 「じゃ、明日な」 「うん、明日ね!!」 にこやかに応えた希美とは対照的に、蘭は気まずそうに顔を歪めた。そんな蘭に気付かれないように、希美はふっとほくそ笑んだ。 「蘭ちゃん、どうかした? 今蘭ちゃんにも言ってたんじゃない? 『明日な』って。いくら”幼馴染みで知った仲”でも、無視するのはよくないと思うよ?」 「あ、うん……ど、どうかな?」 困惑ぎみの悲しい笑みを返した蘭を見て、思わず勝ち誇った笑みが浮かびそうになるのを、希美はぐっと堪えた。そして、わざとらしく顔の前に両手を絡めた。 「ねぇ、蘭ちゃんは来てくれるんでしょ? 私の家。新一が無理なのはショックだけど。蘭ちゃんだけでも、嬉しいわ。あ、そだ。新一の事とか教えてくれる? 事件の事抜きにしてさ。蘭ちゃん幼馴染みでしょ。新一が小さい頃の事とか」 「う、うん……いいよ」 苦しげに、俯きながら返事した蘭に、希美は大げさに喜び、蘭の手を取ってありがとうと言った。 (そう。全部、壊してあげるわ。あなたが持っている彼のものは、全て私のものになるの。二人で築いた思い出さえもね。その優しい性格が、命取りよ) 心の中でくすくす笑う希美の本性を、蘭も新一もまだ知らない。 放課後は、招かれた希美の家でゲームをしながら、蘭は小さい頃の新一との思い出を話した。聞かれるがままに、一つ一つ、胸が締め付けられる思いを感じながら。 にこにこと笑顔で聞いている希美に、蘭は更に追い詰められて行くのだ。 しかし。それから三日経ち、一週間経った頃。 意外にも、希美の機嫌は優れなかった。余裕の表情ばかり浮かべていた彼女だが、ここに来て段々と苛ついていたのだ。 依然新一と蘭は気まずいままで、自分と新一の距離は随分狭まったつもりだった。そんな状態で、新一を奪おうと思えばいつでも出来そうだというのに、自分の心が日に日に苛立っていくのを感じていた。 「新一、教科書私にも見せてくれる? 忘れちゃって……」 「ああ。えっと、何ページだっけ?」 「やだ、もーっ。全然授業聞いてなかったでしょ? ほら、二十七ページ! 『工藤君』って指されたらどうするつもりだったの?」 希美がわざとおどけて教師の真似をして見せたりすると、新一は少し崩した顔で笑って、わりぃわりぃ、と返す。 そんな他愛もない事から始まる会話でも、楽しそうに聞いてくれる。そして、昔約束した願い事も、ずっと守ってくれている。 学校帰りは、完全に彼は自分のもの。遅くなる時必ず待っていてくれる。 なのに希美は、彼と仲良くなればなるほど、その距離が遠くなっていくのを感じていた。 どうしてだか彼女には解らなかった。けれども、周囲が見て近づいていく程に離れていくのを感じていた。 (違う。私、別に新一と距離が離れていってるわけじゃない。最初から、新一は私に対して態度をかえてなんか居ないもの。でも……) 仲良くなって、話す回数も、近くで彼を見る回数も多くなるからこそ判ってきたのだ。希美にも、彼の心がどれ程蘭に向いているのかという事が。 (変わったのは、私の認識ね。本当は、その位……でも、絶対嫌。認めたくないわ、そんな事) 唇を噛み、人知れず俯いた希美も、心の中で、本当は全て気付いていたのだ。 隣の新一が、僅かに退屈そうな顔でシャーペンを回した。それを横目で見て、希美の口元に、溜め息交じりの笑みが零れた。 「……ねぇ、新一。こないだ新一に借りた推理小説、面白かったよ。ありがとう!」 「あ、おう」 推理小説。彼にとって一番食いつきのいい話題だ。けれども、そんな会話を交わしていても、彼の視線は蘭を見つめている。それが、希美には、悔しく悲しい現実だ。 希美は認めようとしなかった。自分の、本当は気付いている怒りと焦燥感の理由であるそれを。 (私なにやってるのよ! チャンスじゃない。今が、絶好の……なのに、彼が私を好きになってくれる気がしないなんて。……いえ、そんな事ないわ。いつか絶対、手にいれてやるのよ!!) 浮かぶ自分の考えを、彼女は無理やり胸の中に押し込めた。いい加減に、そろそろもやもやを吹っ切ってみせる。そう心に決めた希美は、半ば強引に、蘭と遊ぶ約束を取り付けた。 学校帰りによった蘭の部屋で、彼女はゆったりくつろいでいた。 小奇麗に整理された部屋に、未練たらしくも置いてある写真に腹がたった。トロピカルランドで蘭と新一が楽しそうに映るツーショットだ。 揺れる思いを浮かべながら、希美はじっと写真を睨んだ。 (気に食わない……気に食わないわ!) 二人と少しずつ親しい仲になっていくにつれて、解っていく二人の絆に。どうしても、苛立ちは抑えられない。 そんなに悩むのは自分らしくないのはもっともであるが、希美は今部屋に居ない蘭を滅茶苦茶にしてやりたい欲求にもかられた。 お客様用のカップに紅茶を入れて運んできた蘭は、希美が怖い顔で悩んでいるのを見て、恐る恐るその紅茶を差し出した。 希美から家に遊びに行きたいと言われたのに、来るなりだんまりな希美に、彼女はほとほと困り果てていたのだ。 「……ねえ、希美ちゃん」 「何?」 話し掛けてくる悩みの元凶でもある蘭に、何時もより微かに冷たい視線を向けた希美。心なしか、答える言葉にも怒気が混じる。 そんな希美に、蘭は更に困惑の表情を浮かべた。何となくではあるが、それが自分と新一のことに関係しているのだと、蘭は薄々気付いていた。 「……あのさ、新一……私の事、何か言ってたかな?」 「何も言ってないわよ。幼馴染みの子の事、わざわざ私に喋ると思う? ……それとも気になるの? 何か言ってくれないかな、そんな図々しいことでも考えてる?」 途中、意図せず口調が荒くなったのに希美自身気付きながらも、最後まで言い切った。 希美の言葉に、「そんなことないけど……」としゅんとした蘭に、更に腹立てて。 (何よ! まどろっこしい。そんなに新一のことが気になるなら、新一に直接話し掛ければいいじゃない。わざわざ、私経由で探るなんて。 そう。彼は私にあなたの事なんて何も言ってない。……何も言わないのに、心はあなたに向いている。彼はいつもあなたを見つめている。それなのに不幸ぶってるこの女。何様よ。) 「……そんなに気になるなら、新一の事しっかりつかまえとけばよかったじゃない」 希美はポソリと呟いた。 大体からして、新一と蘭の間に溝が出来るように仕組んだのは自分なのだ。であるから、そんな発言は矛盾だらけで自分勝手極まりない。しかし、それでも希美の心は暴走した。 蘭が彼と一緒だった時になかった感覚が、今希美の胸にある。彼が、絶対に自分の手に落ちる事のないような、そんな感覚。 「……つかまえるなんて。私は、新一とは元々何でもなかったから」 「へえ、そう」 俯き答えた蘭を、冷ややかに一瞥した希美は、冷めた顔で目の前の紅茶を口元へ運んだ。と同時に、彼女は顔を顰めた。 よほど淹れ慣れているのだろうか。甘すぎず、苦すぎず……紅茶の香りが生かされて。それは、希美の今の心と裏腹に、温かくて優しい紅茶だった。 希美には、そこがまたなんとも言えず、腹立たしく思えた。 (……いやな感じ) 希美は、悔しげに眉を顰め、息をついた。 がちゃん、と元の位置に戻された紅茶を困惑した眼差しで見つめる蘭を小さく睨んだ。 (いいわ、あんたがどんなにいい女でも……今あんたと新一の間に裂け目が生じてるうちに、彼を私のものにしてやるんだから。それがどんなにバカで空しい思いだったとしても。意地でも、叶えてやる!) 微妙な三角関係が続いていたある日の事だ。新一が、学校途中に事件で呼び出しを受けた。 「悪い、約束の件今日は無理だ」 「いいよ。一日くらい大丈夫。行って来て」 謝る新一に、希美はにこやかに笑って送り出した。そして、その日が彼が好きな推理小説の発売日だったと思い出す。久しぶりに、希美の頭に作戦が浮かんだ。 (やっぱり、読み終えた感動が冷めやらぬうちに、誰かとわかちあいたいものよね!) 本屋まで来た希美は、推理小説の棚を探す。そして、売り切れ前のその本を見つけて微かに微笑み、迷わずそれをレジに運んだ。 翌日、希美は新一の前にそれを大きく突き出した。 「ねえ、新一! ほら。昨日発売の推理小説! 新一、昨日遅くまで事件だったんでしょ? 朝は早すぎて本屋さん開いてないだろうし。私昨日の内に買っておいたんだ。早く読みたいでしょ?? 私、もう読んじゃったからコレ、新一に読ませてあげる」 昨日、結局帰ったのは夜中だという情報を受けて、元々会話をあわそうと買った本がそんなことに役立つ事を知った。 しかし、新一の態度は希美の予想外だった。それを手渡すと、心のない返事が返ってきて、うつろな視線は、いつも通りの彼女の元へ。 もうすぐ、新一と蘭が仲違いしてから、2週間が経とうとしている。 そろそろ、気が変わってもいい頃なのに。 時が経てば経つほど、彼の視線は彼女へ向いていた。 まるで、幾日も絶食状態を続けていた漂流者が、動力源となる食べ物を欲するように。 まるで大きな磁力を持った対立する二極が、必死でくっつきあおうとしているように。 希美は、心底から溜め息をついた。 (ついに推理小説でも、振り向かせられなくなったってわけね…… 全く、禁断症状もここまで来ると……) 本を差し出したままそこにあった手を、ゆっくりと下に下ろし…… 彼の視線を見やって、希美は悲しげに笑みを浮かべ、俯いた。 何時の日かの、園子の言葉が頭を横切る。 彼が好きになるのは、蘭以外にないと。 確かに、今はそう言えるほどの絆があると考えてもおかしくない。 現に、そんなにまで自分に惚れない男は、今までいなかったのだから。 (……ねえ、私のどこが駄目なのよ。私のどこが、彼女に劣ってるって言うの? あんな、私の言葉に囚われて貴方を傷つけるような彼女に。 ねえ、教えて。こっちを向いて) 「……小説、今は読みたくない?」 悲しげに尋ねた希美に、新一は彼女の方を向き苦笑した。 「え? あ……いや。ありがとな。じゃあ読ませてもらうよ」 「うん」 にっこり微笑んで頷いた希美の心の中に、空しさが広がる。 こんなに必死なのに、新一は自分を見てはくれない。 そんなのは、本当に初めてだ…… 「ら……蘭ちゃん………」 「へ?」 つい、その名を口にしてしまった自分が信じられず、希美は内心で困惑した。 怪訝に自分を見つめてくる新一に、とりあえず不信感は持たせないようにと、苦笑しつつ、言い辛そうに言った。 「あ、ううん。蘭ちゃんと、何かあったのかな? って。ほ、ほら……何か最近の二人気まずい雰囲気だからさ」 (……何言ってんの、私。こんな事言ったら……) 考え込むように黙り込んだ新一に希美は慌てた。 彼女の話を出すなんて、自分らしくない。 「あ、あの……聞いちゃまずかった、かな……やっぱり」 いや。むしろ、聞いた事は、彼よりも自分が不味い。 彼が彼女を気にしつづけてるときにこんな話題をするのは。 しかし、彼はそんな希美の様子に苦い笑みを浮かべつつ言った。 「喧嘩してるわけじゃねえよ? 別に気まずくしてるつもりも……ねえんだけどな、オレとしては。 ただ、あいつが妙に気まずい態度取るから、俺自身もあいつに対して気まずくなってただけだ」 彼は、すっと目を閉じて考えた。 あの、あわただしい昼休みの日。さすがにバツが悪くて、あの日一日は自分も気まずかったような気がする。 けれど、それはあの日だけで。 次の日会って、前のような会話が成立するのかと思いきや、 蘭は妙に遠慮した態度をとってきて、新一もそんな蘭に意識してしまって、 相乗効果によって気まずい雰囲気になって。 「蘭が……」 再び、彼の口が動いた事に気付き、希美は彼の顔を覗き込んだ。 新一は、緩く笑顔を作りながら、言葉を続ける。 「俺の事、好きだって言ってくれてた。昔。あれは、勘違いとかじゃない。それは知っていたから……俺が何か言うまでは、別にこれは失恋じゃないと思う。あの時は、あいつが、勇気出して伝えようとした俺から逃げた事に腹立ったけど。でも、そんなの勝手だよな。……最初に逃げてたのは、俺だったんだから」 自分がさっさと気持ちを伝えていればよかったのだ、と彼は言った。 そのせいで、追い詰めてしまったのだと。 希美は悲しげな表情を浮かべながら、彼の話を無言で聞いていた。 「それで、な。色々考えたけど、あいつを追い詰めたの、俺が曖昧なだけじゃないと思うんだ。アイツは、何時だって待っていてくれたから。今になってそこまで追い詰められる事もないだろ。だから、アイツが追い詰められたのは、多分それ以外にも原因があるんだと思う」 「う、うん。そうかも……ね」 突然言われて、どきっとした。顔の筋肉が引きつるのが分かる。 ぐっと拳を握りながら、返事を返す。 新一は真剣な顔で、希美に言った。 「お前、蘭と最近仲いいだろ?だから……何があったのか、分からねーか?」 ふっと浮かべた笑みは優しげで。 けれど、違う。自分に向いて浮かべているその笑みは、 決して自分の事を見て、自分に浮かべられた笑みではない。 彼は、自分の向こう側に居る、蘭を見ていたのだ、と。 気付いて、しまう。 「……ごめん、わからないよ」 これは、嘘。 本当は知ってる……彼女が、何を悩んでいるのかなんて。 でも、もちろんそれを話すわけにはいかないし、 何か都合のいい予測を教えることもできなかった。 嘘なんて、ついた事はなかったのに。 いつも自分なら、なんて言ってただろう。 私が相談に乗ってみるね、とか言っただろうか。 いつもなら、そう言って形だけの相談に乗ったりしたと思う。 けれど…………今は違う。 (……どうして? 彼に、安易にぺろっと喋った言葉で、嫌われたくない。そんな事、今まで一度でも思った事、あった? 皆、私が目をつけた男に用意されてる道は、私の惚れる事一筋だった筈なのに。私も、それを疑わなかったのに) 「悪いな、希美」 「……え?」 「いや、おめーにも心配かけちまっただろ」 そう言って笑った彼の優しい笑顔が、胸にずきん、と響いた。 のしかかるような、重い……想い。 (”心配”なんかじゃないわ……これは。この気持ちは、心配なんかじゃない。余計な答えに導いてしまった自分への、悔しさ。それなのに、そんな事も知らないで…………) 希美の気持ちは、罪悪感と言った類のものではない。 (新一は、彼女のことで深く悩んで。私がそこに関わってるとも知らずに、謝るのね。その希美という女が、諸悪の根源だと疑う事もせずに) 考えれば考えるほど、希美の心の中は苦しく締め付けられた。 新一の、自分と蘭への態度の違いを、段々と思い知ってしまったから。 (どうしてよ! 私につりあう男とか、そんなんじゃないわ。一緒に歩いてて、見栄えるとか……ルックスや名声がある男がつりあってるとか、そんなんじゃなくて。 彼が例えば人を殺して逃げてたとしても。世間の目が彼を最低の男と評価したとしても。それでも私は、彼に嫌われたくない) 希美にとって、それは初めての経験だった。そして、彼女はようやく気づいた。 「あ、そうだ。今日一緒に蘭の家に行ってくれねーか?」 「え?」 「あいつと、今日も遊ぶ約束してんだろ。俺も、ちょっとアイツと話したいことあっから」 「…………解ったわ」 (判っちゃった。今までの私と、今までのどの経験とも違う事。こんなに私、彼の言葉一つ一つに、一々胸が締め付けられる。これが、本当の……私にとって、本当の。初めての、恋なんだ…………) 〜第八話に続く〜 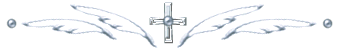 作者あとがきっ!!! 4869番、倖希様のリクで… 「新一と蘭ちゃんの間に割って入ろうとした女の子の話」 第7話ですっ! 勝手にもんもんしてる希美ちゃん(笑) そして、中々手に入らない新一への想いに苛々してる希美ちゃん。 もうちょっとスルーした一週間について触れてもいいかなとも思ったのだけれど、 しつこくならないように、これにとどめておきました。 今回は、希美ちゃんが強く出てた話だけれど……次回は? 次話アップまで、そうかからないかも知れないですし、 もしかしたらまたどっかでつっかかって遅くなるかも知れません^^; さぁ、次話は新一が……!!(何もったいぶってやがる<笑) 完成までしばしお待ちを! それでは、今回もありがとうございました! 次回もよろしくお願いしますv 感想は、例によっていつでもお待ちしてますよ^^v |


