|
☆☆☆6、昼休み? 破局? もう一つの昼休みは、蘭が園子を探して教室に戻って来て、新一と目が合った事から始まった。ずっと、色々な事があって追い詰められていた彼女の瞳に、彼の姿が映ったのだ。視線が重なった瞬間、蘭の胸に痛みが走った。 クラス中の雰囲気も、彼らの心を受けるように幾分強張った。わけの分からない緊張感が場を支配する。 「え、と……その。蘭……」 何かを言わなければ、ともごもご口を開いた新一の手元に、蘭は空の弁当箱を見つけた。可愛らしい作りの、女ものの弁当箱だ。 蘭は、その意味を理解して、すっと目を細めた。 「……ねえ。園子、見なかった?」 気まずそうに尋ねるものの、蘭の心は既にそこにはない。 「さっき……教室に来たけど、希美と一緒に出てった……」 「そう……」 感情のない声で答えるものの、彼女の中では、もう園子が何処へ行ったか等どうでもよくなっていた。蘭の思考を支配するのは、ただその弁当箱の事のみだ。それが判っているクラスメイト達も、気まずさに包まれる。 「”希美”……ね」 辛さを隠すように、蘭の口元に浮かんだ笑みは、更にその場の気まずさに拍車をかけた。 「あ、あのな、毛利。そ、その弁当箱さぁ、俺たちが食ったんだからなっ? 工藤の机に広げてさ……工藤は、食わなかったみたいだけど……」 「へぇ、どうして?」 「あ、いや……だからさ……」 「私には、新一がそのお弁当食べても食べなくても、関係ないよ?」 そっと微笑む蘭の声の、妙な冷静さに、慌てたフォローを入れようとした男子生徒は、黙り込むしかなかった。 誰もが、何とかその気まずい空気を変えようと、何か言わなければと必死になったが、全くそれを変える話題を見つけられない。 「やっぱり、このままじゃダメだよな」 しばらく、沈黙の空気が流れた中で、第一声を発したのは新一だった。 何か考え込んで俯いていた彼が、ぽつりとその一言を口にした時、皆一斉に驚いた顔で彼を見た。何を言う気だろう、とクラス中の誰もが緊張し、強張った。 今から言葉にする事が、現状をいい方に導くものか、それとも悪化させるものか。 自分の事にとことん鈍感な彼の性質は、クラス中の皆が理解していた。内心はらはらしながら見守るクラスメイト達の視線を受け、彼は続けた。 「……蘭、今までごめんな。折角帰って来たってのに、上手く時間とって話せなかっただろ。今度ちゃんと二人で話す時間……あ、いや。まだ昼休みの時間たっぷり残ってるし……今これからでも、外出て二人で話さないか?」 落ち着いた口調で、二人きりになる事を促す彼を見つめ、蘭は少し考えて答えた。 「……そうね」 二人は、滅多に人の来ない校舎裏へと向かった。 無言で、隣を歩く蘭は、どこか寂しそうに、かすかにその大きな瞳を伏せていた。 彼女の、不安や苦しみが、新一の心にとても伝わってきた。 何に、そこまで苦しんでいるのか、その本当の心までは、その時の彼には分かっていなかった。 ただ、彼女を苦しめている原因が全て自分で……彼女にまだはっきりとした答えを示していない事が、彼女を不安にさせている。それだけは、何となく分かった。 そこに転がるいくつかのテニスボールは、前の時間体育だったクラスの生徒が、壁打ちでもして転がしたのだろうか。 彼は足でそこいらのボールを邪魔にならない場所へ蹴り転がし……壁にもたれて、一息ついてから、彼女を見つめた。 「なぁ蘭。やっぱりこのままじゃ駄目だよな。ちゃんとけじめつけねえと」 彼が切なげに呟いた言葉に、蘭の肩はびくりと震えた。 彼が何を言い出すか、彼女の中で決まった答えが出てしまい、震えた声で、彼に返す。 「けじ、め?」 「ああ」 頷いた彼に、微かに震えながら、俯いた蘭。 目元から噴きだしそうになる涙を、必死で堪えて、答えた。 「そう……だね」 二人の気持ちに、けじめをつける時……お互いに、別の意味で腹をくくった。いい意味と、悪い意味と。 蘭は沈んだ雰囲気で、悲しそうに彼を見つめていた。 一方、彼の方は頬を赤らめながら……どきどきと拍動する鼓動を必死で抑えて、 緊張を感じながら、彼女と向き合っていた。 これは、やっと決断した答えだ。ずっと待たせていた彼女に、本当の意味での帰還を遂げる為に必要な。 この決意をするまで、何年の時を要したのだろう。やっと、気持ちを伝える決心がついた。 新一は、先ほどの級友達との会話を頭の中で思い出しながら、目の前にいる蘭の肩をきつく握った。驚き、怪訝な瞳で彼を見上げる蘭に……生唾を飲み込んで、小さく息を吸って。 「蘭、あのな。俺は……」 驚きを隠せずに見開いた彼女の瞳が、ぎゅっと閉じた。心の中が、恐怖に満たされる。 何かを考える前に、勝手に動いた口から、その言葉が出ていた。 「忘れて!」 彼女は新一の言葉を遮って、強い口調で応えた。彼から顔を逸らし、握り締めた拳を更に固く握って。 「へ?」 突然の言葉に、新一は拍子抜けした声を出した。 先ほどの強い決意はどこへやら。いとも簡単に、ぐしゃっと潰れた。踏み折られた花のように、一度折られるとまたすぐ元には戻れない。困惑した様子のまま、新一は固まった。 蘭は、彼同様数秒その姿勢で固まっていたが、目を開けてまっすぐに新一の顔を見た彼女の顔に、迷いはなかった。 「だから。私が、あなたの事好きって言ったの……忘れて」 「………え?」 突然の彼女の言葉に、新一は驚いて言葉を失った。まさかそう言われるとは思っていなかったのだ。 困惑して、何がなんだか分からずに、ただ彼女の次の言葉を待つ。 「何かさ。変だよ、今の私達。元の関係に戻ろう。私、分かったの。最初から私と新一は好きあうような関係になったらいけなかったのよ」 「おい、蘭? 何言って……」 新一には、彼女の言葉の意味が掴めなかった。どうして、彼女がそんな事を言うのか。 「ほら、さ。コナン君にぺろっと言っちゃったでしょ? 私としては、あれって子供相手だと思ってたからなの。ただの、弾みだから。それが偶然新一だったから、話がややこしくなっちゃっただけ。でも、新一に戻ったらそのせいでおかしくなったでしょ? 私達。ずっと気まずくて……」 「ら、蘭……俺は……」 一旦、なえた決意が元に戻るのは、やはり最低でも少しの時間は必要だった。 言う前から忘れてくれと言われて、自分も好きだとは言えなくなってしまった。 どこに行ったらいいのか、行き場のない言葉。ぱくぱく口を動かして、言葉を探す新一をじっと見つめた蘭は、悲しげにふっと微笑んだ。 「ごめんね、勝手に告白して、勝手に忘れてなんて……新一の気持ち引っ掻き回して……酷い女でしょ?」 「違う! 蘭……俺は、俺はお前の事を……っ!」 一瞬だけ、勢いで告白できるかと思われたが、しかしその言葉は続かなかった。 蘭は自分の肩を握る新一の手を、そっと外した。 悲しげな表情に浮かぶ笑みは未だ消えず、彼に言う。 「私ね、新一と恋人同士になるより、今までの幼馴染みとして付き合う方がいい。勝手だけど、いい兄弟みたいな関係でいたいの。長すぎたんだよ、私達。……一緒にいた時間が、長すぎたの」 「蘭……」 「……ううん。本当は、私ずっと新一と、恋人みたいな関係になりたいと思ってたの。まして、ずっと会えなかった時間にそんな気持ちは膨らむばっかりで。でもね、ほら。いざ新一が戻ってきたらさ、何か違うなって。確かに好きだけど…………恋愛感情とかじゃないのかなって」 自分で言った言葉に、心が引き裂かれそうになるなんて馬鹿みたいだ、と彼女は心の中で呟いた。 「けど、お前は……」 あれだけ自信を持っていた事。彼女が、自分の事を好きなのだという事前提で。けれど、きっぱり告げた彼女への言葉が出ない。 悩みこむ彼を見て、そっと小さく微笑んだ。今だけだ、と言い聞かせながら、そっと。 「私ね、よ〜く分かったんだ。自分の中で、嫌な不満ばっかり溜まってくの。新一の事好きだと思うとね。どんどん、自分勝手になってく自分が嫌なの」 「……オレが、探偵だからか? 忙しくて、お前に時間も取ってやれないから……」 新一の問に、蘭ははっとして首を振った。 「違うの! 新一が悪いんじゃなくて……私が、我儘なだけなんだよ。前の幼馴染みとしての関係、結構好きだったんだよ。でも、恋とか愛とか絡むと、まだ付き合ってもいないのにギクシャクして。だから、新一も忘れて。私の気持ちなんて。ね……前の私達に戻ろう?」 彼女はそう言って、俯いた。これ以上、新一の顔を見ていたら、涙が零れそうで。心にも無い事を言うしか、選択肢はなかった。 そんな蘭をじっと見つめ、暫く考え込んでいた彼は、小さく息をついた。 「……お前は、本当にそれでいいのかよ?」 いつもより幾分低い声で、彼は呟いた。 怒っているのか、それとも逆に苦しめてしまったのか分からなくて、顔を上げて彼の表情を見るのが怖かった。 「ごめんね」 言いながら、蘭には判っていた。 これ程、胸が締め付けられると言う事は、本当の気持ちは別れたくないと言う事。 彼が帰ってきた時、凄く嬉しかった。 暗かった世界が急に明るく光に包まれたようだった。けれど、彼が既に自分の告白を聞いている事を知った時から、何も話してくれない彼にずっと不満が溜まって行った。 彼が事件に行くたび、無性に腹が立った。 折角会えたのに、どうしてもっと二人で居る時間を大切にしてくれないのだろう。そんな不満ばかりが出てきてしまっていた。 いっそ、首輪をつけてきつく自分の所に縛り付けておきたいくらいに。 例え、彼と付き合えたとしても、多分その想いはどんどん強くなって、束縛してしまう。 誰よりも、大きな翼を持っている彼を。誰よりも、自由であるべき、自由に羽ばたいていて欲しい彼……自分のせいで、雁字搦めにしてしまいたくなかったのだ。 どこまでも遠く飛んでいく彼に、置いていかれそうで辛かった。希美と話す度に、その気持ちがどんどん強くなっていった。 本当に、大好きだけれど……本当に、大好きだから。昔の関係の方が、よかった。そんな思いが、彼女の心の中に生まれたのだ。 新一は、それ以上何も言わなかった。 時間なんて忘れてずっと俯いていて、予鈴がなった事に気付いて前を見た彼女の目には、もう既に小さくなった彼の後姿が見えた。 「……新一……」 呟いても、彼は振り向かない。いや、恐らくは聞こえてないと言ったほうが正しいであろうか。もう既に小さくなった彼には、それは聞こえる筈もない小さな声だから。 勝手に完結させたのは自分なのに、その後姿を見たら涙が溢れた。泣きながら、その後姿に抱きつきたくなってしまった。 新一は、私に何を言おうとしてたの………? 結末を告げようとしたのだと、あの時思った。だから、彼の口から聞きたくなくて、自分がそれを終わらせたつもりだった。けれど、自分で遮った、彼の言いかけた言葉が気になって。未練がましい自分に、改めて腹が立った。 「馬鹿……」 呟いた言葉が、自分に向けた言葉か、ずっと前を歩く彼に向けた言葉か……それは解らないけれども、ただ一つだけ、蘭は決意した。これ以上、彼を振り回さない、と。 一つ、二つ、零れた涙は、乾ききったその灰色の地面に、微かに潤いをもたらし、すぐに儚く、消えていった。 〜第七話に続く〜 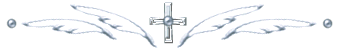 作者あとがきっ!!! 4869番、倖希様のリクで… 「新一と蘭ちゃんの間に割って入ろうとした女の子の話」 第6話ですっ! 今回はちょっとシリアスめ。 やっぱりね、私シリアス系が一番得意なんだわ。 そうなる要素がある話だと、そっちにもってっちゃうの。 直して直して、やっとこれなら……と思える出来になったので、 アップいたしましたv でも、恐らくこれがこの話で一番シリアスな部分だと思いますので。 これ以上に苦しめる事はないんじゃないかと。(私にしては緩いでしょ。) 微妙に蘭ちゃん視点が強めな今回の話。 普段、希美ちゃん視点ですが、彼女の出番がないので。 次話も(更にその次も)出来上がってますが、この話の訂正にあわせて訂正作業したいので、 少し遅くなるかも知れませんが、お待ちくださいませv それでは、今回もありがとうございました! 次回もよろしくお願いしますv 感想は、例によっていつでもお待ちしてますよ^^v |


